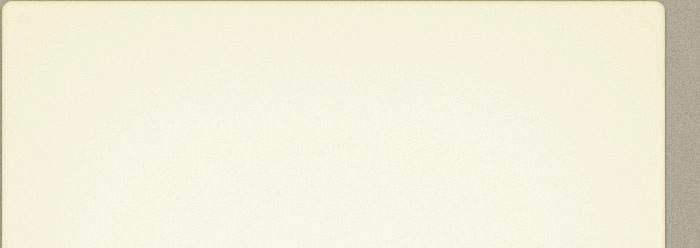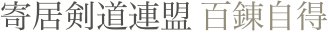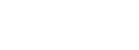真夏日が続く春から初夏にかけての陽気ですが、ゴールデンウィークも暑い日が予報されていました。その初日となった4月28日(土)、日中は25℃を超える真夏日で、午後の子どもたちの稽古では不調を訴える子もいました。夕方になるといくらか気温も下がってきましたが、それでも20℃超。稽古も大変かと思いましたが、剣道場の窓を開け放つと、初夏のさわやかな風が吹き抜け、暑さはそれほど気になりませんでした。
ゴールデンウィークの初日だというのに、たくさんの方にご参加いただき、小中学生若干名を含む約25名の参加者で稽古に励みました。
その翌日4月29日(日・昭和の日)は、毎年恒例の埼玉県下武道大会(剣道の部)が秩父市文化体育センターにて開催されました。今年は第60回の記念大会だそうで、開会行事において記念表彰がおこなわれました。本会(寄居剣道連盟)もこの栄誉にあずかり、清水(都)会長が参列し受賞しました。60回記念おめでとうございました。
今大会には、本会からは審判員として荒木、村田、清水(周)、高野(雅)、倉林など若干名が赴きました。
選手としては、寄居中や男衾中、花園中、寄居城北高など管内の学校が出場するほか、本会からも一般男子の部に出場しました。また、管内の出身で管外の高校に進学した子どもたちもの姿も散見し、その活躍ぶりに眼を細めました。
管内の中学校は、善戦むなしく序盤戦で涙を飲みましたが、高校女子の部で寄居城北高校が優勝しました。おめでとうございます。
また、今年こそは一勝を!と意気軒昂で臨んだ一般男子のチームでしたが、結果は惨敗(;_; 初戦突破はなりませんでした。次に向かって闘志を燃やす選手たちでした。ちなみに出場選手は、先鋒 伊豫部、次鋒 新井、中堅 酒井、副将 島田、大将 清水(周)の布陣でした。ご苦労さまでした。
さて、この時季、全国的には剣道の高段位審査会をはじめ、都道府県対抗や演武大会など、剣道行事が京都方面に集結しています。
4月29日(日)第66回全日本都道府県対抗剣道優勝大会(エディオンアリーナ大阪)
〃 剣道六段審査会(京都市・ハンナリーズアリーナ)
4月30日(月)剣道七段審査会( 〃 )
5月 1日(火)剣道八段審査会(1日目)( 〃 )
5月 2日(水)剣道八段審査会(2日目)( 〃 )
5月 3日(木)〜5日(土)第114回全日本剣道演武大会(京都市武徳殿)
5月 6日(日)剣道称号審査会(京都市)
等々、日本剣道界の一番の行事とも言えるでしょう。
高段位審査会となると、審査員として多数の先生が関わります。そして武徳殿での演武大会にはそういった先生方が、審判員を務めたり、自らも立ち合ったりと、日本最高峰の先生方が集まるときでもあります。特に、5月5日の演武大会における範士や八段の先生方の立合いには注目が集まります。
私ことですが、今年も5月3日(木)の第114回全日本演武大会に出演させていただきました。例年だと、前日にお休みをもらって早めに京都に入り、八段の審査を見学したりしながら、翌日の立合いを迎えるのですが、今年は仕事が休めず、仕事を終えてから、新幹線で夜遅くの京都入りとなりました。しかも新幹線が混んでいて座れず、東京から京都までは立ちっ放しという強行軍でした。
当日の演武では、年々出場の順番が遅くなり、今年の立合いは夕方6時頃になるのではないかという順番でした。前日から行かなくても、当日出発でも間に合うかとも思いますが、やはりこの京都大会では、朝稽古に参加したいという思いがあります。前の晩、チェックインは22:00過ぎとなりましたが、翌朝は5:00に起きて朝稽古の会場の京都市武道センターへ向かいました。範士をはじめ八段の先生がずらりと並ぶ中央に向かって、両外側から参加者が並びま。えらい人数が参加しているので、1時間程度の間に数回できればいいほうですが、稽古するばかりでなく、見ているだけでも大変勉強になります。今年は4人の先生に稽古をお願いできました。参加者の人数が多いので、どの先生かわからず並んでいると、思いがけず全日本の八段戦に出場している先生だったりして、夢中でかからせていただきました。
朝稽古を終えてから、演武の立合いまでたっぷり時間があります。この大会に初めて参加した当時は、開会式から会場に入り浸りで他の人の立合いを鑑賞していましたが、さすがに一日中休みなく立合いが続いているので、ずっと見ていたのでは疲れます。このごろは余裕ができてきて、周辺の観光地などを散策するようになりました。前の晩遅かったこともあり、どこかゆっくり休めそうな場所はないかと、市内をふらふら歩いていたら、なにやらシャレた寺院があり、天井に描かれた双龍図をご開帳しているとあり、おもしろそうだったので立ち寄ってみました。双龍図ばかりでなく、きれいな石庭もあり、けっこう楽しめました。奥のほうでは絵や書などの展示もあり、臨済禅師の『喝』の掛軸にしばし目を奪われました。
その後も近辺を歩き、昼過ぎに武徳殿に戻ったときには歩数計は1万数千歩を越えていました。昨年もこの日歩いた歩数は1万8千歩。一年で一番歩く日です(^.^;ゞ
本大会では、知っている方にもよく出くわします。今年は大学の先輩で、先日の七段審査で合格した方に再会しました。祝福のあいさつを交わし、立合いを拝見しましたが、堂々たる演武でした。また、熊谷や秩父の先生方も出場していました。本会からは私の他もう1名が毎年参加しています。
さて、自分の立合いですが、わずか1分30秒程度の時間でなかなか勝負が決まる立合いも少なく、これまで引き分けが多かったかと思いますが、勝敗を数えるとやや負け越し気味かなといったところです。今年も緊張しながら迎えましたが、立合い前に本部席に埼剣連会長の山中先生の姿を拝見し、こりゃ情けない立合いはできない!と気持ちを引き締め、充実した気持ちで臨めました。結果2本勝ちをおさめ、自分でもビックリしてしまいました。決していい立合いとは言えなかったと思いますが、気持ちは充実していたと感じています。また精進してまいりたいと思います。
さて、私ことが長くなりましたが、翌5月4日(金)は寄居剣道連盟の一級審査会でした。中学生の男女それぞれ10名前後の約20名くらいの受審者でした。実科、形、木刀稽古法をおこない、それぞれによく稽古していることが感じられました。若干不安な子もいましたが、おおむね問題なく、全員が合格となりました。形の出来栄えがあまり芳しくなかったこともあり、審査後に役員から指導を受ける場面もありましたが、6月の初段審査に向けて、さらなる稽古に取り組んでいただきたいと思います。
当日の役員は、清水(都)会長、柴﨑、荒木、清水(周)、久保田、高野(初)、雨宮、土屋、島田、伊豫部、宮下事務局長の11名でした。
審査会終了後、翌日に控えた寄居地方武道大会の会場設営をおこないました。上記役員の他さらに役員が増え、寄居城北高校の生徒たちも例年のごとく出てきてくれて、さらに一級審査を受けた中学生にも手伝ってもらい、円滑に会場の準備を整えました。大会の盛会を期するとともに、出場される選手のご武運をお祈りします。